読書に関するインタビュー
1 杉田 剛(すぎた ごう)さん:架け橋としての読書
取材日 平成30年12月26日(水)
聞き手 生涯学習課 清家 矢括
文責 生涯学習課

杉田 剛さん プロフィール
宮崎商工会議所専門経営指導センター課長補佐。中小企業診断士。大学卒業後、東京で通信キャリアに勤務。2007年宮崎商工会議所入所。5年地元商店街活性化事業に取り組んだのち、経営支援全般を担当するほか、みやざきスタートアップセンターを立ち上げ、ビジネススクール、ビジネスプランコンテスト、商談会の企画・運営を展開。前宮崎県読書活動推進委員。
子供の頃 本はよく読んでいましたか?
ほとんど読んでいませんでした。読書感想画や読書感想文が苦手で、夏休みの最後のほうまでやらずに残していました。
中学生の頃「どん松五郎の生活」というボリュームのある課題図書があり、読むのが大変で、感想文の内容がほとんどあらすじになってしまいました。
住んでいる所は近所に本屋がなく、本を買うという発想がまずなかったんです。
学校図書館は使っていなかったのでしょうか?
中学生の頃、学校図書館にはよく行っていました。でもいわゆる読書、というような本ではなく、図鑑とか、日本の風景や苔寺などの写真集等を見ていました。
本をよく読むようになったのはいつ頃からでしょうか?
社会人になってからです。
どんなに自分が精一杯勉強しても、能力を高めようとしても、その発想などかなわないな、という方々と(仕事で)出会ったとき、せめて共通の言葉を持ちたい、彼らの考えの背景を知りたいと考え、知識の習得として、主に経営やビジネスの本を読み始めました。
最初の10年はインプットが98~99%を占めていたように思います。次第にアウトプットの割合が増えていったけれど、これからもインプットは永遠に続くことになると思います。
自分の読書は、娯楽というよりは、知識の習得、スキルアップの読書です。でも、知識を得る読書も楽しいものです。

どんなジャンルの本を読んでいますか?
仕事柄、経営、ビジネス、ITに関する本、趣味で住まいに関する本を読んでいます。 民間企業のインターネットサービスがあり、雑誌も980円で読むことができるので、それを利用したりしています。
本選びの参考にしているものはありますか?
口コミ、有名な人、自分が注目する人がツイッターやフェイスブックでいいよ、と薦めているものはすぐに注文したりしています。
注目する起業家等は皆忙しい人のはずなのに、かなり本を読んでいます。
本はどんな方法で入手していますか?
定額放題のインターネットサービスがあるんですけれど、それを使って結構読んでいます。これですと11冊目を読むには1冊読み切るしかないので、強制的に量を読むことができるんです。
電子書籍も読みますが、知識を習得するときは線を引いたり余白に書くことができるので、読書はやはり紙がいいですね。
図書館は利用していますか?
子どもと2週間に一度は県立図書館を利用しています。子どもの本はいいものがありますね。自分もはまって子ども用の本を読むことがあります。大人も全ての分野を深く知る必要は無い、子ども本は分かりやすくコンパクトにまとめてあるので便利ですね。伝記ものもスティーブ・ジョブズなど出ているので感心しました。
県立図書館のビジネス関連の本は新しい、いい本がいろいろ入っていてうれしいです。
ガイ・カワサキ(Guy Kawasaki)さんという方の本と出会ったのも県立図書館です。もともとアップルにいらして、今シリコンバレーで投資をしている方です。県立図書館でその本に出会い、それ以来YouTubeで話しているのを見たりして、その考えにあこがれ、とても影響を受けました。セミナーでもその方の言葉を借りたりしています。
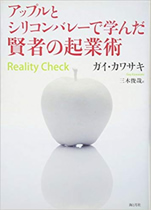
『アップルとシリコンバレーで学んだ賢者の起業術』
(ガイ・カワサキ/著 海と月社)
「おすすめしたいこの1冊」的な本はありますか?
『ミライの授業』(瀧本哲史/著 講談社)です。
自分と同じ県の読書活動推進委員の中学校の先生からご紹介いただいたんですが、読んでみたら中学生向けではあるものの大人にもおすすめできるもので、実際私も職場の5,6人に薦めました。

『未来の授業』(瀧本哲史/著 講談社)
どんな本でしょう?
瀧本さんはマッキンゼーというコンサルティング会社の出身で京都大学で教えているようです。この本は史実に基づいて書かれていますが、イノベーションをどう起こしたかという、従来の捉え方とは異なるアプローチで書かれています。
例えばナイチンゲールは看護師だったけれど、統計家でもあったんです。病院をきれいにすることによって、病院内で病気になる人を減らすよう病院内の環境を衛生的に保ち、その改善結果を統計図にまとめ女王陛下に箴言(しんげん)したんです。その表の書き方が優れているので未だに踏襲されているんだそうです。
そのほか、宮崎出身の高木兼寛のこともとりあげています。森鴎外と脚気の原因について論争がありました。鴎外は存在しない細菌が原因だと主張し、兼寛は患者をつぶさに観察して栄養不足を主張したんです。実際にはビタミン不足が原因でした。新しいことを生み出すとき、何もないところから突拍子もないことを考えないと生まれないと思いがちですが、兼寛は現実に忠実に寄り添うことで解決策を導きだしました。兼寛のそのアプローチにすごく感激した思いがあります。
そのほかこの本のおすすめのポイントはありますか?
この本は世界を変えたイノベーター20名を取り上げる、というのがテーマで19人までがとりあげられていますが、最後の20人目は「君だ!」、という構成になっているんです。自分も「うおーっ」となりました。
杉田さんはいつ本を読んでいるのですか?
すきま時間で読んでいます。1日で読破しようとか、構えると読めません。たとえば打ち合わせで、相手から30分遅れますと連絡があるとその待ち時間などで読みます。背表紙、目次を見てここだけは読もう、というような読み方をしています。

なぜ本を読むのだと思いますか?
読書で古今東西色々な知識を学ぶことができ、色々な人に出会えます。新しいアイデアは結局既存のものの掛け合わせでしかないんです。本によって昔の知識が一瞬にして手に入り、延長線上の未来につながる。また、東洋の考え方、西洋の考え方等の架け橋になるのも本ではないでしょうか。
本は地理的な架け橋だけでなく未来への架け橋にもなるということでしょうか。もう少し詳しくそこのところをお聞かせいただけますか?
メタップスという会社の佐藤航陽さんという人がいらっしゃるんですが、そもそもそれがなんで生まれたのか考えてない人がほとんどだけれど、昔のことをしっかり学び、考えると、分野や時代が異なっても将来予測ができるものがあり、投資に役立つと著書の中で言っているんです。
例えば電気の普及と、インターネットの普及は同じ路線を歩んでいると。電気は周囲を明るく照らすだけだったのが、うちわに電気が入り扇風機となり、ほうきに電気が入り掃除機になったわけです。一方インターネットも最初はパソコンでぱちぱちやるだけだったのが、携帯電話に移ってきて、そのうち車、冷蔵庫にもインターネットが入ってきているわけです。電気とインターネットの歩みから将来予測ができると。

『未来に先回りする思考法』
(佐藤航陽/著 ディスカバー・トゥェンティワン)
思考の癖として、地理的な範囲として、自分が生まれた地域内で考えてしまう癖と、時間的な範囲として、生まれた時代以降のことしか考えない癖があると思います。ただ地域外や過去のことは与えられたもの、所与のもの、として発想が及ぶことがあまりない。
しかしそもそも何のためにそれが生まれたか考えると、昔からやっているというだけで続いているもの、実は既に役割を終えたものがたくさんある。
そう考えたときに読書は自分が生まれた地域以外のことや、自分が生まれる以前のことを知るにも役立ちますし、過去から未来、自分で新しいものごとを考える架け橋になってくれています。





