| 1. |
はじめに |
| |
(1) |
生活リズムの向上は、心身の発達の基本となります。 |
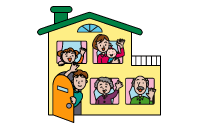 |
| |
(2) |
生活リズムの基本は、家庭の中でまず形成されます。 |
| |
(3) |
生活リズムの乱れは、家庭環境の悪化と関係します。 |
| |
(4) |
生活リズムの崩れは、抑うつや孤立を引起こします。 |
| |
|
|
| 2. |
子育て相談から |
| |
(1) |
子どもは、何歳になったらひとりで寝かせた方がいいのでしょうか。 |
| |
(2) |
子どもが夜中に起きてきて、リビングに居る私たち夫婦の座っているテーブルの周りをぐるぐると回るのです。 |
| |
(3) |
不登校の息子がいます。本人の好きなことばかりさせておいて良いのでしょうか。 |
| |
|
|
| 3. |
生活リズムと親子関係 |
| |
(1) |
「関係」ということ(中学2年不登校男子)(お化粧して登校する女子中学生) |
| |
(2) |
子ども「理解」のレベル(小学校5年生の子どもを持つ母親の話) |
| |
(3) |
「対話」ということ(家出した高校生) |
| |
|
|
| 4. |
親が子どもにしてあげられること |
| |
(1) |
守る(社会的、経済的、精神的、物理的に) |
| |
(2) |
一緒に遊ぶ(対等に遊ぶことの是非) |
| |
(3) |
話を聞く(聞くというのは、listenであり、askではありません)
(「でも」や「が」ではなく、肯定的な受け止めが求められます) |
| |
|
|
 |
| 5. |
「話を聞く」ことの重要性 |
| |
(1) |
最後まで話を聞きましょう(基本)。 |
| |
(2) |
近づいて、子どもの顔を見ましょう(笑顔)。 |
| |
(3) |
子どもの話を受け止めましょう(反射)。 |
| |
(4) |
会話がずれないようにしましょう(事実はに事実で)。 |
| |
|
|
| 6. |
「あたたかい言葉がけ」を目指して |
| |
(1) |
平静な気分を維持しましょう。 |
| |
(2) |
冷静でおられない時は、一呼吸置きます(深呼吸)。 |
| |
(3) |
怒るときは、「雷のち晴れ」の要領で(梅雨の長雨は避けましょう)。 |
| |
(4) |
「干渉しないが放っておくわけではない」の心境で。 |
| |
(5) |
お互いの自主性の尊重を心がけましょう。 |
| |
(6) |
関係が変化することで、いろいろなものが変化し始めます。 |
| |
(7) |
ひとりひとりに説明書なんてありません(「うちの子の取扱説明書ってないのですか?」)。 |